教員 出版物/メディア出演等の情報

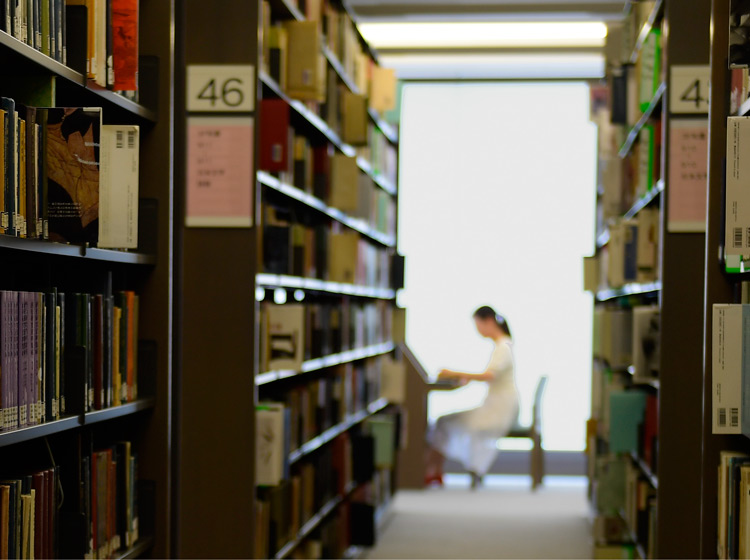
本学の教員による著書、出版物、メディアへの掲載、出演等の情報についてご紹介いたします。
| 掲載日・ 出版日 |
所属 | 教員名 | 媒体名等 | 内容 | 関連リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW 2025年6月23日 |
観光コミュニティ学部まちづくり学科 | 石崎裕子 | 『アエラ』2025年6月30日号(No.31)、10頁‐13頁、朝日新聞出版 | 「巻頭特集 令和の専業主婦 専業主婦は生きづらい―働き続けることがデフォルトの時代に」において、取材協力し、コメントが掲載された。 | 6/9,6/12のAERA DIGITAL アエラデジタル(旧AERAdot)に先行展開 |
| NEW 2025年6月12日 |
観光コミュニティ学部まちづくり学科 | 石崎裕子 | 「AERA DIGITAL アエラデジタル(旧AERAdot)」(朝日新聞出版『AERA』編集部) | 「『専業主婦は死ねってこと?』 官民あげての『女性活躍推進』で増す生きづらさ」(特集「令和を生きる『専業主婦』は幸せなのか?」)において、取材協力し、コメントが掲載された。 | AERA DIGITAL アエラデジタル(旧AERAdot) |
| NEW 2025年6月9日 |
観光コミュニティ学部まちづくり学科 | 石崎裕子 | 「AERA DIGITAL アエラデジタル(旧AERAdot)」(朝日新聞出版『AERA』編集部) | 「“バリキャリマウント”に沈黙の令和の専業主婦 家事・育児のやりがい実感もなぜか肩身が狭い」(特集「令和を生きる『専業主婦』は幸せなのか?」)において、取材協力し、コメントが掲載された。 | AERA DIGITAL アエラデジタル(旧AERAdot) |
| 2025年4月12日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 日本経済新聞 2025年4月12日(土)朝刊NIKKEIプラス1 |
土曜朝刊別刷り“NIKKEIプラス1”のカラダづくりに掲載された記事「植物性たんぱく質を取ろう 摂取量は減少傾向、豆乳活用」にコメントが掲載された。 | 日本経済新聞社 |
| 2025年3月30日 | 文学部現代文化表現学科 | 要 真理子 | 水声社『芸術を知らぬ建築家たちへ 寓話「カリフのデザイン」仕儀』 | 英国の画家にして小説家のウィンダム・ルイス(Wyndham Lewis, 1882-1957)の著作『カリフのデザイン(The Caliph's Design)』(1919年)の翻訳です。日本ではあまり知られていませんが、この翻訳を通じてルイス、そして英国前衛芸術に関心をもっていただけたらと願っています。 | 水声社 |
| 2025年3月12日 | 文学部人文学科 | 水谷 長志 | 新著『ミュージアムの中のライブラリでアーカイブについても考えた:体験的MLA連携論のための点綴録』 | MLA連携は3つの館界にあって,その呼称・考え・課題が共通されて久しい。そもそもこの三者の連携についての議論は,1994年にアート・ドキュメンテーション学会(当時,研究会)が国立国会図書館において創立5周年を期して開いたシンポジウム「ミュージアム・ライブラリ・アーカイヴをつなぐもの―アート・ドキュメンテーションからの模索と展望」に始まる。本書は,その企画・司会を担った著者が東京国立近代美術館という館の屋根の下でアートライブラリとアートアーカイブを構築した三十余年の軌跡を点綴したものである。 *本書の出版は,跡見学園女子大学学術図書出版助成によるものです。 |
樹村房 |
| 2024年12月2日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 日本英語交流連盟「日本からの意見」ウェブサイト 「日本経済の顔・津田梅子の現代的意義」 | 24年夏、五千円札に肖像画が採用されて、新しい日本の顔となった津田梅子。津田梅子とは誰なのか。なぜ現代日本は彼女を必要とするのか。梅子を世界に紹介する小論。 | 一般社団法人 日本英語交流連盟 |
| 2024年11月5日 | 観光コミュニティ学部まちづくり学科 | 石崎 裕子 | 『アエラ』2024年11月11日号、P.66-P.67(朝日新聞出版) | 介護や育児などでやむを得ず専業主婦になった女性たちを取り上げた「[女性×働く]やむを得ず専業主婦」(連載[女性×働く]の新シリーズ「専業主婦」第2回)において、取材に協力し所見を提示。コメントが掲載された。 | |
| 2024年11月2日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | ABCラジオ(朝日放送ラジオ) | 朝日放送が近畿広域圏を対象に放送しているAMラジオ放送局の番組「土曜日やんなぁ?」に生出演し、「ヘルスケアCLUB」コーナーで大豆や豆乳の健康効果について解説した。 | ABCラジオ「土曜日やんなぁ?」 |
| 2024年9月4日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 楽しいニュース「たんぱく質の動植物バランスの重要性と豆乳の賢い取り入れ方『「豆乳による食生活&体調改善調査結果発表会」』開催!」 | 「リセッ豆乳プロジェクト」(日本テトラパック株式会社)は、9月4日(水)にメディアを対象とした「豆乳による食生活&体調改善調査結果発表会」を開催した。当日は、本調査の監修者である石渡から、調査結果とたんぱく質を摂取する際の動植物バランスの重要性について説明を行った。 | 楽しいニュース |
| 2024年8月25日 | 文学部人文学科 | 笹島 雅彦 | 東京新聞・中日新聞日曜版 | 〈大図解〉「対テロ戦争」と題する特集記事で、笹島雅彦による「対テロ戦争20年の決算――平和構築挫折の教訓」(跡見学園女子大学文学部紀要第57号)との論文を参考に各種データを紹介している。記事末尾で参考文献として笹島論文を明記してある。特に、ブッシュ政権が同時多発テロ事件を「戦争行為」と位置づけ、途中から「民主国家建設」を目標とするなど政策の変遷を紹介した点や、膨大な戦争コストなどについて、引用している。 | <大図解>対テロ戦争(No.1677):東京新聞 TOKYO Web (tokyo-np.co.jp) |
| 2024年6月25日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 櫻川 幸恵 | 著書(教科書)『金融論』 | 金融の勢力図は変わろうとしています。市場の存在感が大きくなり、銀行業もまたその影響を受けることになると予想されます。本書は、金融の本質をとらえながら、基本的な考え方や概念について正確な理解を促すように説明を加えており、また変化の激しい金融の世界に対応できる力を養うことを狙いとしています。基礎編は、私の跡見学園女子大学での講義やゼミの内容をもとにしています。学生の皆さんの反応や声も参考に内容を修正した箇所もたくさんあります。本書を通じて「覚える」のではなくて「考える」癖を身につけることができるように意図したつもりです。ぜひ手に取って読んでみてください。 | 新生社 |
| 2024年5月1日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 『豆類の百科事典』 国本牧衛・石本政男・村本光二・加藤淳・谷口亜樹子 編、朝倉書店 |
主要な豆類の生産、機能性、加工利用、歴史、食文化などを網羅した536ページの事典の中で、第Ⅲ章 機能性―栄養・味覚・生体調節機能―、〔イソフラボンの生体調節機能〕Ⅲ-44 女性の健康に及ぼす効果(pp.276-277)を執筆した。 | 朝倉書店『豆類の百科事典』 |
| 2024年4月20日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 図書新聞 | 図書新聞6面に拙著『変容するインドネシア』(めこん)に関する書評が掲載された。 | |
| 2024年2月16日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 中西 希和 | NHK Eテレ「はなしちゃお! ~性と生の学問~」(2024年冬号(2)プライベートゾーン×スポーツジェンダー学) | NHKの性教育番組「はなしちゃお! ~性と生の学問~」(2024年冬号(2)プライベートゾーン×スポーツジェンダー学 2/16(金)22:30-22:59)で、水着の歴史について解説した。 | NHK Eテレ「はなしちゃお! ~性と生の学問~」(2024年冬号(2)(プライベートゾーン×スポーツジェンダー学①) |
| 2024年2月10日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 中西 希和 | 読売新聞 朝刊(15面 ニュースの門) | 「女性像 時代を先取り」の記事において、着せ替え人形「バービー」の衣装に関して、取材協力を行った。 | |
| 2023年12月22日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 政治山 | 11月25日、跡見学園女子大学と大塚製薬株式会社共催による「女性の健康セミナー〜正しく知って対処するPMS!~」が開催された。その中で、女性のライフプランに欠かせないホルモン変動をテーマに、ライフステージにに応じた健康対策の重要性について講演した。 | PMSや生理痛、正しく知って婦人科かかりつけ医に相談を(2023/12/22 政治山) |
| 2023年12月23日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞朝刊 書評欄 23年12月23日 | 年末恒例の「2023年の3冊」に、村上陽一郎氏が小川著『逆襲する宗教 パンデミックと原理主義』(講談社選書メチェ)を挙げている。 | |
| 2023年12月10日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 著書『変容するインドネシア』(めこん) | 「イスラーム化」と「デジタル化」をタテ軸、多様性をヨコ軸として、急速に変貌しつつ国際社会で台頭する現代インドネシアを活写。 | めこん |
| 2023年11月22日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | テレビ朝日「 健求者 ~こだわりの元気食」 2023年11月22日出演 |
健康を追及している研究者の研究内容とそのこだわりの食事を紹介するミニ番組。大豆と女性の健康について20年以上、研究を続けてきた研究者のこだわりの元気食とは? | テレビ朝日「 健求者 ~こだわりの元気食」 |
| 2023年11月21日 | 文学部現代文化表現学科 | 渡邉 大輔 | 著書『謎解きはどこにある――現代日本ミステリの思想』 | 「快適至上主義(倍速視聴・どんでん返しの否定)」の世界で名探偵はどこに向かうのか。 文学、ライトノベル、ドラマなどのミステリ作品を考察し、現代ミステリの変化を論考した評論書 |
南雲堂 |
| 2023年11月14日 | 文学部人文学科 | 栗田 秀法 | 朝日新聞 | 「(耕論)博物館の危機と未来」にて、「科博クラファンで見えた 「館の命、国が見殺し」専門家が訴える危機」と題されたインタヴュー記事が掲載された。 | 朝日新聞朝刊13面(2023年11月14日付) |
| 2023年10月18日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 石崎 裕子 | 読売新聞 | 「New 門『女性誌』 主婦、妻、母へ 寄り添う1冊」(生活部 大石由佳子記者による特集記事)において、女性誌の変遷からみえてくる女性の生き方の多様化について所見を提示。コメントが掲載された。 | 読売新聞 朝刊8面(2023年10月18日) |
| 2023年9月25日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 中西 希和 | 日本経済新聞 夕刊(8面 くらしナビ) | 「ファッションドール」と呼ばれる着せ替え人形の歴史や役割の変化について取材を受け、説明した内容が掲載されている。 | 「着せ替え人形、元祖は人間サイズ 最新トレンド服を発信」(なるほど!ルーツ調査隊、日本経済新聞 電子版) |
| 2023年9月21日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞朝刊(9月21日) | オピニオン面に「ASEANと真の対等関係へ」というテーマで所見を提示。 | |
| 2023年9月14日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | おいしい健康/まめけん「女性の健康と 『大豆』の関係」 | 女性特有の心身の不調改善に役立つ成分を含む大豆。その魅力と日常の食生活への取り入れかたについて、インタビュー形式で解説した。 | おいしい健康 |
| 2023年8月15日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 日本英語交流連盟ウェブサイト | 日本英語交流連盟ウェブサイト「日本からの意見」に、日本語及び英語で「福田ドクトリンを継承し現代に生かそう」( Let us Revive the Fukuda Doctrine to Mark a Fresh Start Today.)と題するエッセイを寄稿。 | 日本英語交流連盟 「日本からの意見」(Japan in Their Own Words) |
| 2023年5月~ | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 小関 孝子 | 日本経済新聞、北海道新聞、東京新聞、中日新聞、他 | 『夜の銀座史』(ミネルヴァ書房)の書評が、5/6日本経済新聞、5/21北海道新聞、6/3東京新聞、6/4中日新聞に掲載された。また、共同通信配信の著者インタビューが20紙以上の地方紙に掲載された。 | |
| 2023年4月22日 | 文学部人文学科 | 水谷 長志 | 編著書『ミュージアム・ライブラリとミュージアム・アーカイブズ』(樹村房)刊行 | 本書は、国立美術館、公立美術館、私立美術館、国立博物館のそれぞれに個性と語るに十分な歴史を有する4館のミュージアムの中のライブラリとアーカイブズについて、現場に軸足を置きつつ語られている。 | 樹村房 |
| 2023年3月30日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 小関 孝子 | 『夜の銀座史』(ミネルヴァ書房)刊行 | かつて「女給」と呼ばれた女性たちの視点から銀座の夜に焦点をあて、明治中期から1960年頃までを通史で描く。 | |
| 2023年2月7日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 著書 【『逆襲する宗教 パンデミックと原理主義』(講談社選書メチェ)】 | 新型ウイルス危機の到来で、急速に注目されるようになった宗教と現代社会の問題を、米国、ロシア、インド、インドネシア等国別に解説する。 | 講談社BOOK倶楽部 |
| 2022年12月27日 | 文学部コミュニケーション文化学科 | 宮津 多美子 | 読売新聞夕刊(05ページ)「世界史アップデート」 ~アメリカ南北戦争の実相~ | 研究成果を反映した最新鋭を、広く知られた従来説と比較しながら紹介する歴史シリーズ「世界史アップデート」の「アメリカ南北戦争の実相」を取り上げた記事で、奴隷解放宣言の歴史的評価に関するコメントが取り上げられた。 | |
| 2022年7月12日 | 文学部コミュニケーション文化学科 | 宮津 多美子 | 読売新聞夕刊(05ページ)「世界史アップデート」 ~アメリカ独立革命~ | 研究成果を反映した最新鋭を、広く知られた従来説と比較しながら紹介する歴史シリーズ「世界史アップデート」の「アメリカ独立戦争」を取り上げた記事で、独立戦争期のマイノリティー研究に関するコメントが取り上げられた。 | |
| 2022年3月30日 | 文学部コミュニケーション文化学科 | 宮津 多美子 | 書籍『人種・ジェンダーからみるアメリカ史―丘の上の超大国の500年』 | 世界の模範「丘の上の町」となるべく築かれたイギリス植民地の小さな共同体が20世紀に超大国アメリカへと変貌するまでの北米史を、人種・ジェンダー史を中心にナラティヴで描いた書籍を出版した。 | 明石書店 |
| 2022年9月27日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 石崎 裕子 | 出演【「ABEMAPrime」(アベマプライム)特集「どうなる?令和の専業主婦“女性版骨太” で超人化?家事育児の分担を考える」】 | テレビ朝日のインターネット放送局「ABEMATV」内の報道番組「ABEMAPrime」(アベマプライム)2022年9月27日(火)21:00~23:00(生放送)において、特集「どうなる?令和の専業主婦“女性版骨太” で超人化?家事育児の分担を考える」にZoom出演した。現代において専業主婦は生き方の選択肢の一つであることや現代女性のキャリア、ライフコースの多様化について話した。 | 「ABEMAPrime」(アベマプライム)番組公式ホームページ https://news-prime.abema.tv/ |
| 2022年3月11日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 横堀 応彦 | ステージナタリー「横堀応彦・呉宮百合香・太下義之・内野儀が語る、国際共同制作の課題と可能性」 | 2022年2月18日に登壇した公開座談会の様子を一般向けにレポートした記事がステージナタリーで公開された。 | ステージナタリー |
| 2022年2月24日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 石崎 裕子 | 【withnews(運営会社:朝日新聞社)】 | 朝日新聞社金澤ひかり記者による署名記事「専業主婦が大学院に行ったらダメですか?批判された当事者の思い」において、現代の専業主婦について所見を提示した。 | 「専業主婦が大学院に行ったらダメですか? 批判された当事者の思い(金澤ひかり記者)」(withnews、2022年2月24日掲載) |
| 2022年2月18日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 横堀 応彦 | 2021年度舞台芸術国際共同制作事業 8つの国際共同制作を振り返る―オンライン座談会―~プロセスオブザーバーの視点から~ | 国際交流基金が主催する公開座談会にモデレーター兼パネリストとして登壇し、オブザーバーを担当した作品の事例報告を行い、今後の国際共同制作について議論した。 | 国際交流基金(JF)オンライン配信用YouTube チャンネル |
| 2022年2月10日 | 文学部人文学科 | 矢島 新 | ちくま新書『日本美術の核心-周辺文化が生んだオリジナリティ』 | 日本美術のオリジナリティについて、様々な角度から分析した1冊。第1章「入ってきたもの・出ていったもの」、第2章「デザインへの傾斜」、第3章「そこにあるのは「美」か「真理」か」、第4章「教養があってこそ味わえる」、第5章「文字と絵の幸福なコラボレーション」、第6章「素朴を愛する」、第7章「わびの革命」、第8章「庶民ファーストなアート」、第9章「多様なスタイルの競演」、第10章「周辺のオリジナリティ」 | |
| 2021年12月24日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | コロナ禍と体験型イベント | 本書は、2020年から続くコロナ禍によって、演劇やライブ、美術館、展示即売会、スポーツ観戦といった「体験型イベント」は、どのように被害を被り、耐え忍び、また変わりつつあるのかを研究対象としている。 同書中、第2章「日本発ポップカルチャーを通じたファンコミュニティの交流 ――COVID-19とイベントのオンライン化に関する検討」を担当した。 |
blog水声社 |
| 2021年9月21日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 横堀 応彦 | 共著「Okada Toshiki & Japanese Theatre」 | 英国パフォーマンスリサーチブックス社が発行したピーター・エッカーソル他編「Okada Toshiki & Japanese Theatre(岡田利規と日本の演劇)」に日本演劇の国際性に関する論考を寄稿した。 | ドイツ日本研究所 |
| 2021年8月27日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 郷 香野子 | 著書 【『事例ベース意思決定(CBDT)によるマーケティング』(千倉書房)】 | 新しい製品は、どのように評価されるのか。経済学で用いられてきた事例ベース意思決定理論(CBDT)をマーケティングに適用、不確実性下における消費者の意思決定を探索的に考察。 | 千倉書房 |
| 2021年7月24日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 松井 理恵 | 西日本新聞第2面(総合面) | 日本統治時代の朝鮮半島で生まれた詩人・作家である森崎和江氏の作品の韓国語翻訳(2020年11月出版)に関する記事。 | 西日本新聞me 九州ニュース 原郷に渡った森崎文学 |
| 2021年7月10日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 日本経済新聞 読書面 | 日本経済新聞社読書面に拙著『自分探しするアジアの国々』(明石書店、2021)が短評で紹介された。「歴史から現代的な課題までもが凝縮され、入門書にとどまらない読み応えがある」との評。 | 日本経済新聞 |
| 2021年5月21日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 「現代ビジネス」 | 講談社、情報サイト「現代ビジネス」に『自分探しするアジアの国々』著者インタビューが掲載された。コロナ禍のアジアにおける宗教復権の可能性、アジアの若者が創造する現代文化等について語った。 | 講談社「現代ビジネス」 |
| 2021年4月22日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | アニメツーリズム白書2021 | 「『アニメツーリズム協会』が目指す、アニメツーリズムの今と未来」と題した記事において、富野由悠季氏(アニメ監督・演出家・脚本家・作詞家・小説家・アニメツーリズム協会会長)・鈴木則道氏(アニメツーリズム協会専務理事)とのパネルを記事化したもの。 | アニメツーリズム白書2021 |
| 2021年3月30日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 石崎 裕子 | 「配偶者男性 なんと呼ぶ?」(『読売新聞』2021年3月30日朝刊、23面) | 【取材協力】読売新聞東京本社編集局生活部野口季瑛記者への取材協力。 「配偶者男性 なんと呼ぶ?」(『読売新聞』2021年3月30日朝刊、23面)において、近年の女性誌における女性読者の配偶者の表記・呼び方の変化について、所見が掲載された。 |
|
| 2021年3月20日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 単著、明石書店 | 『自分探しするアジアの国々:揺らぐ国民意識をネット動画から見る』を出版。本学の講義「現代アジア社会論」の経験から生まれた現代アジアの入門書。 | 明石書店 |
| 2021年1月26日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 宮崎 正浩 | 朝日新聞デジタル | 女性取締役の比率を上げても企業業績には変化がみられないが、男女の勤続年数差を縮小した企業は業績が向上した。女性取締役の枠を決めてしまうとかえって逆効果になりかねない。まずは男女の区別なく同じように昇進の機会を与え、人材を育てることが重要と指摘した。 | 朝日新聞デジタル |
| 2021年1月16日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 松井 理恵 | 東京新聞第23面(地域の情報) | 日本統治時代の朝鮮半島で生まれた詩人・作家である森崎和江氏の作品の韓国語翻訳、出版に関するインタビュー記事。 | 東京新聞 TOKYO Web 「森崎和江さん『慶州は母の呼び声』翻訳 追憶の朝鮮半島、韓国でも」 |
| 2020年12月24日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 土居 洋平 | インタビュー記事「Iターン移住者の活躍と寛容な農山村コミュニティ」 | 農山村へのIターン移住について、その背景や現状と可能性を、山形県をフィールドにした調査研究に基づき紹介したインタビュー記事。 | いい引っ越し.com |
| 2020年12月2日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 東京新聞第20面(特報欄) | 「鬼滅ヒット 相乗効果続々」という記事の取材に応じ、アニメの聖地巡礼についてのコメントが掲載された。 | |
| 2020年11月20日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 赤松 瑞枝 | 監修・寄稿 キャリズム | 転職関連情報を掲載しているサイト。育児中かつ転職活動をしている女性のために働き方のヒントを提示するというコンセプトの記事を監修し、且つ、子育てと両立しやすい働き方の選択肢についてコメントした。 | 女性の働き方を考える上で重要な考え方~子育てママの様々な働き方の選択肢~ |
| 2020年11月17日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | 東京新聞朝刊総合 | 「コロナ禍 回復 欧米下回る」というニュースの中、アパレル業界の不振、その影響をうけて女性ファッション誌『JJ』の休刊について解説した。 | |
| 2020年11月6日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | TBS朝の情報番組「グッとラック!」 | 1975年創刊の女性ファッション誌『JJ』の休刊についてその原因をコメントした。 | |
| 2020年11月5日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | TIFFCOM2020 セミナー「「アニメツーリズム協会」が目指すアニメツーリズムの今と未来」 | 東京国際映画祭(TIFF)併設のマルチコンテンツマーケットTIFFCOMにおいて開催されたセミナー「「アニメツーリズム協会」が目指すアニメツーリズムの今と未来」において、一般社団夫人アニメツーリズム協会富野由悠季会長・鈴木則道専務理事と共に登壇し、モデレータを担った。 | TIFFCOM |
| 2020年10月26日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 遺産相続に関する法律相談サイト 「相続弁護士ナビ」 | 「健康寿命を伸ばす食事について跡見学園女子大学の石渡教授に取材しました!(後半)」 後半は健康な食習慣やクオリティ・オブ・デスに関するインタビュー内容。 |
相続弁護士ナビ |
| 2020年10月26日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 遺産相続に関する法律相談サイト 「相続弁護士ナビ」 | 「健康寿命を伸ばす食事について跡見学園女子大学の石渡教授に取材しました!(前半)」 前半は主に研究内容やゼミでの取り組みに関するインタビュー内容。 |
相続弁護士ナビ |
| 2020年9月2日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 日経ヘルス 2020年10月号 | 特別付録『大豆パーフェクトブック』(全44ぺーじ)にインタビュー記事が掲載された。 ・P4:「和食」代表・大豆は世界が認めた健康食材 ・PP22-23:大豆で女性ホルモンUP ・PP30-31:骨も乳癌も・・・大豆で“命”を守る |
株式会社 日経BP |
| 2020年4月17日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | 朝日新聞朝刊社会 NEWSQ3 | 「3密と広告減 ファッション誌の苦境」というタイトルで、新型コロナウイルスの出版界への影響をNEWSとしてとりあげた記事。その中でコロナ禍がファッション雑誌のビジネスモデルそのものを直撃している理由を説明した。 | |
| 2020年4月10日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 寄稿 アニメツーリズム白書2020 | アニメツーリズム白書2020(企画・監修:一般社団法人アニメツーリズム協会)に「メディアミックスによる“アニメ”ツーリズムの対象拡大と、その将来性」と題する解説を寄稿した。 | アニメツーリズム白書2020 |
| 2020年3月6日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 一般社団法人 日本英語交流連盟 | 日本英語交流連盟ウェブサイト「日本からの意見」に、日本語及び英語で「新型肺炎:効果的な対外広報を」(New Coronavirus: Need for effective Public Diplomacy)と題するエッセイを寄稿。 | 日本英語交流連盟ウェブサイト「日本からの意見」 |
| 2020年3月5日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞 3月5日朝刊 | 毎日新聞 3月5日朝刊オピニオン欄(発言)に、「新型肺炎、効果的対外広報を」を寄稿。新型ウイルス問題に関する対外広報について、非常時対応の必要性を訴えた。 | 毎日新聞ウェブサイト |
| 2020年2月6日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 著書「Japan’s Public Diplomacy at the Crossroads」 | 米国ルートリッジ社が発行したスノー・カル編”Roultledge Handbook of Public Diplomacy"第2版の日本の対外文化広報外交に関する章を執筆した。第2版では東日本大震災以降の日本の対外文化広報外交についての概説を加筆した。 | Routledge |
| 2020年2月1日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)2月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 模索するデジタル民主主義」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネスレポート |
| 2019年12月1日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)12月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 デジタル化社会への機体と懸念」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネスレポート |
| 2019年11月21日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 一般社団法人 日本英語交流連盟ウェブサイト「日本からの意見」 | 日本語及び英語で「2020年以降の海外日本語教育のゆくえ」(Whither is post-2020 Japanese-language education abroad going?)と題するエッセイを寄稿。 | 日本英語交流連盟ウェブサイト |
| 2019年10月25日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 東南アジア文化事典 | 第3部「日本と東南アジアの社会文化交流・第13章 東南アジアの中の日本 / 日本の中の東南アジア」に編集協力し、同章中の「東南アジアの日本語教育」「東南アジアの日本研究」などの項目を執筆。 | |
| 2019年10月3日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 朝日小学生新聞 | 2019年10月3日付け朝日小学生新聞一面にインドネシアの首都移転計画について、インドネシアの首都移転計画に関する「ジャカルタの首都機能は人口が増えて限界に達している」との小川忠教授のコメントが掲載された。 | |
| 2019年10月1日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)10月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 日本はインドネシアとともに戦ったか?」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネスレポート |
| 2019年8月7日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 朝日新聞朝刊 国際面(8面) | 特集記事「南方からの声:語り継ぐ戦争」において、以下のコメントが掲載された。(東南アジアで相次ぐ日本軍政関連出版の)「背景にアイデンティティー探しの側面があると、跡見学園女子大の小川忠教授(現代アジア論)は言う。(中略)小川教授は『東南アジアにとって、日本による占領は、独立やアイデンティティーの確立に関わる歴史であり、資料を残す機運が青年たちの間で高まっている』と指摘する。」 | 朝日新聞 |
| 2019年8月 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)8月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 日本軍政期史料が語る歴史の多面性」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2019年7月 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)7月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 インドネシアの大学生は寛容性を失いつつあるのか」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2019年6月 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 日本軍政期インドネシア史料展ワークショップ | 日本軍政期インドネシア史料展実行委員会が開催したワークショップ「インドネシアの日本軍政期の史料と文化政策」にて、「ジャカルタ日本文化センターで見つけた啓民文化指導所のDNA」と題する講演を行った。 | |
| 2019年6月 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)6月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『ジャワのイスラム』が勝敗を決した大統領選挙」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2019年5月28日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 日本英語交流連盟 | 日本英語交流連盟ウェブサイト「日本からの意見」に、日本語及び英語で「平成の文化交流の基盤を固めた竹下登首相 再評価」(“Prime Minister Noboru Takeshita’s Legacy in Cultural Exchange: A Reassessment“)と題するエッセイを寄稿しました。 | 日本英語交流連盟 |
| 2019年4月 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)4月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 肥満化するジャカルタ」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2019年2月28日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 毎日アジアビジネス レポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト3月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『大統領選挙:新しいが、何やら古いソーシャルメディアの戦い」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2019年1月20日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 毎日アジアビジネス レポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト1月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『大統領候補プラボウォ・スビヤント その手強さの源泉」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2018年12月30日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)12月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『イスラム・ロックとアイデンティティー』」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2018年11月22日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)11月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『日本語学習大国インドネシアでの新たな試み』」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2018年10月24日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 審査員 外務省「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」 | 平成30年9月22日外務省主催、「国際問題プレゼンテーション・コンテスト」にて、「私の提言~日本の広報文化外交:日本をよりよく知ってもらうために」をテーマとする大学生・大学院生の発表を審査、講評を行い、同講評が外務省ウェブサイトに10月24日掲載された。 | 外務省 |
| 2018年10月22日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 寄稿 毎日アジアビジネスレポート | 毎日新聞社・毎日アジアビジネス研究所が発行する「毎日アジアビジネスレポート」(会員向けウェブサイト)⒑月号に、「連載コラム:小川忠のインドネシア視線 『スラウェシ地震とテロ・リスク」と題するエッセイを寄稿した。 | 毎日アジアビジネス研究所 |
| 2018年10月21日 | 文学部人文学科 | 小川 忠 | 講演 さがみはら国際交流ラウンジお茶会/「インドネシアを知ろう」 | さがみはら国際交流ラウンジお茶会にて、「インドネシアを知ろう」と題して市民向け講演を行った。多民族・多宗教国家インドネシアの現在を解説し、その魅力を伝えた。 | さがみはら国際交流ラウンジお茶会 |
| 2020年2月9日 | 文学部人文学科 | 加藤 大鶴 | 米沢日報デジタル | 遊学館ブックス「どっこい方言は生きている」の書評。 | 書評 遊学館ブックス「どっこい方言は生きている」 |
| 2020年1月30日 | 文学部人文学科 | 加藤 大鶴 | 遊学館ブックス「どっこい方言は生きている」公益財団法人山形県生涯学習文化財団 | 山形県における方言の受容、地域アイデンティティ、方言話者の当事者性、これからの方言などをテーマとしてシンポジウムを行った。本書はその書籍化である。加藤は主たる企画者であった。 | |
| 2019年1月20日 | 文学部人文学科 | 加藤 大鶴 | 山形新聞 | 書評「文章を味わう 書きたくなる」 中村明著『日本語の作法』青土社 | なし |
| 2019年9月10日 | 文学部人文学科 | 加藤 大鶴 | Jタウンネット | 山形の有名な方言である、(1)を「イチカッコ」と呼ぶ現象について、その由来についての仮説を述べた。 | 山形県民はなぜ(1)を「いちかっこ」と読むのか 専門家に見解を聞いた |
| 2019年12月5日 | 文学部人文学科 | 水谷 長志 | From ‘MLA Collaboration’ proposed by the Library & Archives of the National Museum of Modern Art, Tokyo to ‘MLA Collaboration’ as the New Type of the Research Method for Education in University, Lee Ungno Museum, Daejeon, Korea, International Symposium: Museum ・ Human ・ Future. | 韓国太田広域市のLee Ungno Museum, Daejeon, Korea が開催した国際シンポジウム-International Symposium: Museum ・ Human ・ Futureにおける、第3セッション"Future"において、MLA連携を美術館から大学にシフトさせて、その汎用性を特に学部学生の調査研究メソッドの涵養の側面から論じた。 講演邦題「ミュージアムの中のライブラリ&アーカイブで構想した〈MLA連携〉から大学の教育現場で提案する新たなリサーチ・メソッドとしての〈MLA連携〉へ 」 |
Lee Ungno Museum, Daejeon, Korea |
| 2019年11月25日 | 文学部人文学科 | 水谷 長志 | 「ミュージアム・ライブラリの原理と課題-竹橋の近代美術館での30年から伝えられること / 伝えたいこと」『現代の図書館』日本図書館協会, Vol. 57, No.3, 2019.11.19, p.107-117. | ミュージアム・ライブラリの原理と課題について、竹橋・東京国立近代美術館のアートライブラリでの30余年の体験的実践から、特に欧米美術図書館員の先達が示し、筆者自身が繰り返し参照系としてきた5つの命題、すなわち、[1]つながること(co-operation)・[2]多様性(diversity)・[3]一人図書館員(OPL: One Person Librarian)・[4]アート・ドキュメンテーション学会(JADS: Japan Art Documentation Society)の成立とMLA連携の萌芽・[5]一国の主題専門図書館における「部分と全体」(artels vs monoliths)を紹介し、今後の課題の提起を試論して、特集「博物館・美術館の図書室をめぐって」の巻頭総論とした。 | 日本図書館協会/ JLA出版物 |
| 2018年10月13日 | 文学部人文学科 | 水谷 長志 | 「MLA連携は学部学生の新たな調査研究手法になるだろうか?」 アート・ドキュメンテーション学会/2018年度第11回秋季研究集会(2018年10月13日 於お茶の水女子大学共通講義棟1号館 ) |
「MLA連携の事例を探す」という課題を最終レポートにして、学期最終講義日に選抜された8名ほどがプレゼンテーションを行うというスタイルの講義で、学芸員資格の必修科目である博物館情報メディア論を慶應、東大、青山学院ほかで講じてきた。今春学期には花蹊記念資料館を有する本務校の司書資格課程でも同様の課題を試みた。M(useum)とL(ibrary)の二項関係に加えて、関連するA(rchive)を発見して、Aを媒介項とするMLAのトライアングルの構造を体験することが、学部学生にとって新たな調査研究手法の開発につながる可能性を拓くことを、課題プレゼンテーションの事例を踏まえ報告し、提案するものである。 | アート・ドキュメンテーション学会ホームページ |
| 2019年7月25日 | 文学部人文学科 | 矢島 新 | 『芸術新潮』 | 雑誌『芸術新潮』2019年8月号の特集「ゆるかわアート万博」で、日本のゆるかわアートを紹介。 | |
| 2019年7月21日 | 文学部人文学科 | 矢島 新 | NHK Eテレ「日曜美術館」アートシーン | 三井記念美術館特別展「日本の素朴絵―ゆるい、かわいい、たのしい美術―」の監修者としてVTR出演を行った。 | |
| 2019年2月25日 | 文学部人文学科 | 矢島 新 | 監修【『マンガでわかる「日本絵画」のテーマ(誠文堂新光社)』 | 日本絵画の多様な画題をマンガを用いて解説する書の内容面を監修 | |
| 2019年2月10日 | 文学部人文学科 | 矢島 新 | 著書【『ゆるカワ日本美術史』(祥伝社新書)】 | 日本美術の中に見出されるゆるくかわいい造形の系譜を抽出し、それらが日本美術のオリジナリティの核心に近い部分を担っていることを論じた。 | |
| 2018年12月15日 | 文学部人文学科 | 森 まり子 | 信濃毎日新聞(2018年12月24日)文化欄「東西アジア移民を比較 被害、加害、歴史的経緯・・・多様な視点」 | コーディネーター:上條宏之・信州大名誉教授。パネル:臼杵陽・日本女子大教授、長沼宗昭・元日大教授、芝健介・東京女子大名誉教授、小川幸司・高校教員、森。対応者:小林信介・金沢大准教授ほか。研究者の他に、長野県を中心とした市民の方々も約70名参加。パネル講演として「満洲移民とパレスチナへのユダヤ人移民━<二つの近代>を比較して━」を行いました。 | |
| 2019年12月1日 | 文学部人文学科 | 峰松 和子 | 「英語教育」12月号(大修館書店)Vol.68 No. 10. P.33 タイトル:リスニングから導入するリーディング:「概念駆動型」アプローチ |
リスニングから導入してリーディングへと導く「概念駆動型(concept-driven)」アプローチを紹介。このアプローチは基礎レベルから上級レベルまで応用可能であるが、今回は特に語彙や文法に苦手意識を持つ学習者、または英語の文字を読むことが苦手だと感じている学習者に焦点を当てた。このアプローチでは、文字から「データ駆動型(data-driven)」で始めるのではなく、音声インプットを複数回与えながら「概念駆動型」の授業を進めると、学習者が自分の持っている背景知識も活かしながら、「概念の活性化」「推論する力」などを働かせ、自ら内容を把握しようとする。そこからテクストを読む動機が高まる。また、リスニング確認時にペアワークを取り入れることにより、さらに内容を理解したいという動機も高まる。最終的にはリスニングによる「概念駆動型」アプローチはテクストの内容理解の足場づくりになると考えられる。 | |
| 2019年9月18日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | 朝日新聞朝刊 | 朝日新聞「明日へのLesson」において、「元編集長が雑誌制作を伝授」と題する記事が掲載された。現代文化表現学科「ライティング特殊演習」の授業内容について紹介。 | 朝日新聞 |
| 2019年7月26日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | ドキュメンタリー映画『モデル 雅子を追う旅』 | キャリア30年、50歳で他界したモデル「雅子」の半生を追ったドキュメンタリー映画。生前、雅子と接点のあった人たちへのインタビューで構成されているが、その中で一緒に仕事した雑誌編集者として雅子のモデルとしての存在についてコメントした。映画公開1週間、行われたトークイベントの7月31日にゲストとして登壇した。 | モデル「雅子」を追う旅 公式ホームページ |
| 2018年12月4日 | 文学部現代文化表現学科 | 富川 淳子 | 日本タウン誌・フリーペーパー大賞2018 | 2011年から続く、日本タウン誌・フリーペーパー大賞の特別審査員として、その授賞式に参加。授賞式は上野の国立科学博物館で開催され、審査員を代表して、大賞の講評のほか、海外媒体部門賞や新創刊部門賞なのについて講評を行った。 | 日本タウン誌・フリーペーパー大賞2018 |
| 2018年11月7日 | 文学部現代文化表現学科 | 要 真理子 | 東京学芸大学主催・美術教育セミナー・講演会「子どもの描画と感性と創造性を考える−西洋児童美術教育の思想の系譜から−」 | 子どもの描画研究の歴史を振り返りながら、それぞれの時代のなかで、子どもの描画、感性、創造性にどのように光が当てられてきたかを考え、これからの乳幼児の描画や表現活動の意味や可能性を論じた。 | 東京学芸大学ホームページ |
| 2019年1月6日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 鳫 咲子 | 【テレビ朝日「サンデーステーション」】 |
記事のアクセス件数によってランキング形式でニュースを伝えるコーナーで、PTAが給食費を集めることの問題、どのような形に改めるべきかについてコメントが紹介された。 | テレビ朝日「サンデーステーション」 |
| 2018年12月31日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 鳫 咲子 | 【朝日新聞(西部本社版)】 | 福岡県柳川市における「給食費集め なぜ保護者が」という記事において、「PTAに給食費を集めさせるのは、未納ゼロでもまるで江戸時代」というインタビューが掲載された。 | 朝日新聞(西部本社版)12月31日記事 |
| 2018年12月16日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 鳫 咲子 | 出演 【TBSテレビ「噂の!東京マガジン」】 |
「横浜で中学校の弁当大量廃棄?ママ達激怒」というコーナーで、中学校給食の必要性・地域格差、デリバリー給食についてコメントが紹介された。 | TBSテレビ「噂の!東京マガジン」 |
| 2018年10月9日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 鳫 咲子 | 出演 【NHK「ハートネットTV」】 |
NHKハートネットTV「“おうち食堂”で温かいごはんを」に出演して、おうち食堂を通して、子どもの生活を周りの大人がどう支えていけば良いかについて話した。 | NHK「ハートネットTV」 |
| 2019年8月8日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 曽田 修司 | 書籍『紛争地域から生まれた演劇』 | シリア、パレスチナ、イランなど世界の「紛争地域」で、なぜ演劇は創られ、どのように演じられているのか。本書により、私たちは未知の紛争について知り、それが自分たちと直接関わりのある出来事であることを発見し驚愕する。欧米、アフリカ、そしてアジアの各地で。本書は、世界の歴史・文化・宗教・政治が、語り手・演じ手・観客という個人の視点を介して交錯し共鳴する、圧巻の「現代・世界・演劇」探究の書である。 【編者紹介】 林英樹(はやし ひでき) 演劇企画団体テラ・アーツ・ファクトリー代表、国際演劇協会日本センター理事、「紛争地域から生まれた演劇」総合プロデューサー。 曽田修司(そた しゅうじ) 跡見学園女子大学マネジメント学部教授、国際演劇協会日本センター常務理事・事務局長。 |
ひつじ書房 |
| 2019年11月16日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 細川 淳 | ニッポン放送「おしゃべりラボ - しあわせsocial Design」 | 研究し、実践を啓蒙している「従業員所有事業」に関して語った。 また、跡見学園女子大学での教育・研究活動についても言及。 |
|
| 2019年11月9日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 細川 淳 | ニッポン放送「おしゃべりラボ - しあわせsocial Design」 | 研究し、実践を啓蒙している「従業員所有事業」に関して語った。 また、跡見学園女子大学での教育・研究活動についても言及。 |
|
| 2019年8月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 細川 淳 | 日本経済新聞朝刊 | 日本経済新聞朝刊、「私見卓見」に掲載。 | 日本経済新聞 |
| 2019年2月9日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 細川 淳 | 大宮経済新聞 | 大宮経済新聞 取材記事掲載「地場産業の課題解決型授業 埼玉の女子大生が提案、新しい皮革製品」 マネジメント学科の山田(満)ゼミ、細川ゼミ、中西ゼミ合同で、埼玉県産業支援課、埼玉皮革関連事業協同組合との連携によるPBL (Project Based Learning)を実施。 その様子が同新聞に掲載された。 | 大宮経済新聞 取材記事掲載「地場産業の課題解決型授業 埼玉の女子大生が提案、新しい皮革製品」 |
| 2019年4月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 雑誌「公益・一般法人」 | コラム「景気のゆくえ」で、「イベントの多い2019年度」というタイトルで寄稿。 | 全国公益法人協会機関誌「公益・一般法人」 |
| 2019年3月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 雑誌「実践自治Beacon Authority」 Vol.77 春号 | 「発想 Conception 統計と政策立案―どのように政策に活用するか」を寄稿 | イマジン出版 |
| 2019年3月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 雑誌「景気とサイクル」 | 書評『「データ分析の力 因果関係に迫る思考法」伊藤公一朗著/光文社新書』を寄稿。 | 景気循環学会 |
| 2019年2月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 雑誌「公益・一般法人」 | コラム「景気のゆくえ」で、「景気拡大の実感が乏しい長寿景気」というタイトルで寄稿。 | 全国公益法人協会機関誌「公益・一般法人」 |
| 2019年2月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 雑誌「第一生命経済研レポート」 | 巻頭の「時評」で「上がらない賃金とルイスの転換点」というタイトルで寄稿。 | 第一生命経済研究所 |
| 2019年1月17日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 島根県 | 島根県平成30年度第2回統計利活用研修会で「経済と労働統計-賃金の動き―」というタイトルで講演。 | 島根県ホームページ |
| 2018年12月27日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 著書「Comparison of the Potential Competitiveness of Asian Countries 」 | 小巻泰之編"The Future of Southeast Asian Countries Population Change、 Climate Change、 Management of Japanese Companies and Competitiveness"の第7章を担当。東南アジアや南アジアの潜在競争力を計測した。 | 八千代出版 |
| 2018年12月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 『季刊国民経済計算』平成30年度第2号No.164 | 「1次統計におけるシェアリングエコノミーの把握」という論文を発表した。シェアリングエコノミーをGDP統計に加味するには、1次統計にどのような工夫が必要かを検討した。 | 内閣府経済社会総合研究所 |
| 2018年12月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 寄稿 雑誌「一般・公益法人」 | 雑誌「一般・公益法人」の景気のゆくえというコラムに、「変調を来たす景気」というタイトルで寄稿。 | 全国公益法人協会 |
| 2018年11月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 寄稿 月刊誌「統計」 | 月刊誌「統計」に「シェアリングエコノミーの計測と一次統計」という論文を寄稿。 | 一般財団法人日本統計協会 |
| 2018年11月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 寄稿 Japan SPOTLIGHT | 日本を紹介する英文誌Japan SPOTLIGHTに"Statistical Understanding of the Sharing Economy"と題する文章を寄稿。 | 一般財団法人国際経済交流財団 |
| 2018年10月1日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 山澤 成康 | 寄稿 雑誌「一般・公益法人」 | 雑誌「一般・公益法人」の景気のゆくえというコラムに、「QEの見直しと景気判断」というタイトルで寄稿。 | 全国公益法人協会 |
| 2019年3月 | マネジメント学部マネジメント学科 | 許 伸江 | 平成30年度 復興庁クラウドファンディング支援事業事例集 | 東日本大震災からの復興を盛り上げるための復興庁のクラウドファンディング支援事業の外部審査員としてエントリー審査を実施。審査を通して見てきた被災地で生まれた新しいビジネスについて、「地域へ与えたインパクト」としてメッセージを寄稿した。 | |
| 2019年11月26日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 【サンデー毎日】12月8日号 | 巻頭カラーグラビア〔ゼミナール・ラブ!〕偏差値より研究テーマが面白い!23 で研究と取り組みが紹介された。『跡見学園女子大学 マネジメント学部生活環境マネジメント学科 石渡尚子研究室 食事を楽しむ「共食」で高齢者の孤食を解消』 | サンデー毎日 |
| 2019年8月8日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 毎日新聞 |
石渡ゼミでは2020東京オリンピック・パラリンピックに向け、3年間にわたり訪日外国人を対象とした熱中症啓発活動に取り組んでいる。今夏、浜離宮恩賜庭園にて8月5日(月)~10日(土)に開催した「熱中症啓発イベント」が取材を受け、毎日新聞に記事が掲載された。 | 毎日新聞2019年8月8日 東京版「熱中症予防 訪日外国人らに啓発 跡見女子大・石渡ゼミ /東京 」 |
| 2019年8月8日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | The Mainichi | 石渡ゼミでは2020東京オリンピック・パラリンピックに向け、3年間にわたり訪日外国人を対象とした熱中症啓発活動に取り組んでいる。今夏、浜離宮恩賜庭園にて8月5日(月)~10日(土)に開催した「熱中症啓発イベント」が取材を受け、毎日新聞に記事が掲載された。 | The Mainichi, August 11, 2019 (Mainichi Japan) |
| 2019年1月28日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 『毎日が発見』No.181 | 2月号の「今月の発見」ページに掲載された「天然のサプリメント『大豆』を再確認!」で、大豆に含まれる健康に役立つ成分や石渡流の大豆の摂取方法を紹介した。 | 株式会社毎日が発見『毎日が発見』2019年1月28日発行 |
| 2018年11月10日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 『ヘルシスト』vol.252 |
栄養士養成以外の学科で唯一、農林水産省が実施する第2回食育活動表彰でボランティア部門大学等の部の消費・安全局長賞を受賞したことからHealthist Topic 「食育活動」最前線に石渡ゼミが紹介された。 | ㈱ヤクルト本社『ヘルシスト』2018年11月10日発行 |
| 2018年10月25日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | ㈱マガジンハウス 『croissant』 No.984 |
雑誌『クロワッサン』2018年11/10号の第2特集「食べて痩せる、元気になる。『大豆パワー』の秘密」で、大豆や大豆食品をもっと健康的に摂取するコツを紹介。大豆中心の日本食が世界に注目されていること、大豆に含まれる有効成分をすべて摂取するために「丸ごと食べる」習慣をつけること、そしてその習慣を継続することを推奨し、最後は大豆から考えるエシカル=環境に配慮した食事について言及している。 | マガジンハウス クロワッサン |
| 2019年4月15日 | マネジメント学部生活環境マネジメント学科 | 石渡 尚子 | 『クロワッサン特別編集 女性のカラダを守る大豆発酵食健康法。』 | PP.6-8「大豆中心の日本の食生活を、今、世界中が追いかけています。」というテーマでインタビュー記事が掲載された。更年期の症状など、女性への健康効果がよく知られている大豆は、現代に求められる“エシカルな(環境に配慮した)食材”であることを提言。また、大豆の成分を効果的に摂取するための4つのルールについて解説した。 | マガジンハウス |
| 2019年12月5日 | マネジメント学部マネジメント学科 | 許 伸江 | 日刊工業新聞 | 東京都墨田区のオープンファクファクトリーイベント「第8回スミファ-すみだファクトリーめぐり」の取組みにおいて、ゼミ生がインスタグラムの公式アカウントを作成し、企業紹介したことが掲載された。 | |
| 2019年12月4日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 磯貝 政弘 | 伊東市主催・セミナー講師「伊東市観光プロモーション事業・ブランド研究会 第1回セミナー」 | 静岡県伊東市の新しい観光プロモーション事業を検討する「ブランド研究会」のキックオフ・セミナーとして、「伊東の“観光”を考える」と題する講演とディスカッションを実施。観光地ブランド確立の要件を示し、伊東市の観光地としての現状を分析、課題を提示し、その解決策を提案した。 | |
| 2019年11月10日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 磯貝 政弘 | 一般社団法人岡崎市観光協会主催・講演会「観光まちづくりセミナー」 | 愛知県岡崎市で活動する観光事業者、ボランティアガイドなどを対象に、「観光が岡崎を変える」と題して講演。観光マーケティングの視点から、最新の研究成果に基づく消費者の旅行に関する意向や行動パターンを紹介したうえで、岡崎市の観光戦略への提案をした。 | |
| 2018年11月19日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 磯貝 政弘 | 出演【NHK「おはよう日本」】 |
NHK おはよう日本!【11/19(月)放送】で、「ゆるキャラ」について、観光コミュニティ学部観光デザイン学科の磯貝政弘教授がコメント出演した。磯貝教授は、地方のPRの取り組み・地域振興に詳しい方として紹介され、ゆるキャラの有効性を解説した。 | 本学HPニュース |
| 2018年1月16日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 磯貝 政弘 | 講演 【鹿児島県市議会議員研修会】 | 「この時代の旅の可能性-成熟社会の旅行者ニーズと観光事業」と題して、鹿児島県内の市議会議員研修会で講演。1990年代後半以降の旅行者ニーズの特徴を各種調査データに基づき示したうえで、これからの観光事業のあり方について提言した。また、NHK大河ドラマがもたらす効果についても言及した。 | |
| 2019年11月2日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | Kent Wired.com | アメリカ・オハイオ州のケント州立大学ファッションスクールにて日本発のポップカルチャー・ファッションについて講演し、交流活動等に参加したことに関する取材記事が掲載された。同講演は在デトロイト日本国総領事館からの依頼によるもの。 | The Fashion School hosts lecture on fashion, style, popular Japanese culture |
| 2019年11月2日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | YOUMACON2019 | アメリカ・ミシガン州のポップカルチャーイベント”ヨウマコン”の在デトロイト日本国総領事館提供セッションにて、日本のポップカルチャー文化に関する講演を行った。 | YOUMACON2019 |
| 2019年10月31日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | BG Indipendent News | アメリカ・オハイオ州のボーリング・グリーン州立大学にて日本発のポップカルチャーについて講演し、交流活動等に参加したことに関する取材記事が掲載された。同講演は在デトロイト日本国総領事館からの依頼によるもの。 | Talk on Japanese pop culture today at BGSU |
| 2019年10月24日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 日本テレビ「スッキリ」 | 日本赤十字の献血事業における広報について、近年人物写真とは別にアニメ・マンガなどのキャラクターが活用されてきている理由について解説した。 | |
| 2019年7月23日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社が運営するビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」にて、「バンナムがあえて「リアル施設」を強化する狙い ゲーム・アニメの世界に入れるMAZARIAとは」を寄稿した。 | 東洋経済オンライン |
| 2019年7月10日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社が運営するビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」にて、「大英博物館で異例ずくめのマンガ展開催の意味 国外開催のマンガの展覧会として最大規模」を寄稿した。 | 東洋経済オンライン |
| 2019年4月17日 | 観光コミュニティ学部観光デザイン学科 | 中村 仁 | 東洋経済オンライン | 東洋経済新報社が運営するビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」にて、「「池袋プリンス」ワンフロア丸ごと大改装の中身」を寄稿した。 | 東洋経済オンライン |
| 2019年7月1日 | 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科 |
石崎 裕子 | 「広報たからづか」2019年7月号(No.1250)、13頁 | 男女共同参画週間特別寄稿「男女共同参画週間によせて」 2019年度「男女共同参画週間」のキャッチフレーズ(「男女共同参「学」」「知る 学ぶ 考える 私の人生 私がつくる」)にちなんだ寄稿。 |
宝塚市ホームページ(電子書籍版「広報たからづか」2019年7月号、13頁) |
| 2019年2月28日 | 観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 | 篠﨑 健司 | 北海道新聞 | 平成31年2月25~27日にかけて、ゼミの代表メンバーが北海道南富良野町を訪問し、同町において地域資源を活かした活性化を目指し、アウトドア体験や地域住民等と一緒にワークショップを実施したことについて、北海道新聞より取材を受け、その際の記事(北海道新聞 2019 年2月28日(木)日刊紙掲載)として掲載されたもの。 | 北海道新聞 |
| 2018年10月29日 | 心理学部臨床心理学科 | 松嵜 くみ子 | 山口豊一共著「学校心理学にもとづく教育相談―『チーム学校』の実践を目指してー」 | 子ども一人ひとりの援助ニーズに応じ、充実したサポートをするために、学級担任、教育相談担当、生徒指導主事などの教師、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフ、公認心理師や教師を目指す学生など、学校教育に携わる方に向けて、教育・学校に役立つ心理学をわかりやすく解説した | 金子書房 |
| 2019年6月25日 | 心理学部臨床心理学科 | 板東 充彦 | 書籍『公認心理師実践ガイダンス3 家族関係・集団・地域社会』 | 国家資格である公認心理師取得を目指す者に向けた実践ガイダンスの編集を行った。主にグループ・アプローチ、コミュニティ・アプローチを担当するとともに、理論篇の「公認心理師が『地域社会』にかかわるために」を執筆した。 | 木立の文庫 |
| 2019年10月 | 心理学部臨床心理学科 | 前場 康介 | 『健康心理学事典(丸善出版)』 分担執筆 |
健康心理学における重要項目を読者に提示し、「興味深く読み通せる学問事典」を目的として刊行されたものである。執筆を担当した『高齢期の健康教育』では、高齢期に特有の健康状態に焦点を当て、広く予防的観点から個人・集団・社会を対象とした様々な取組みについて事例を交えながら紹介した。 | 丸善出版株式会社 健康心理学事典 |

